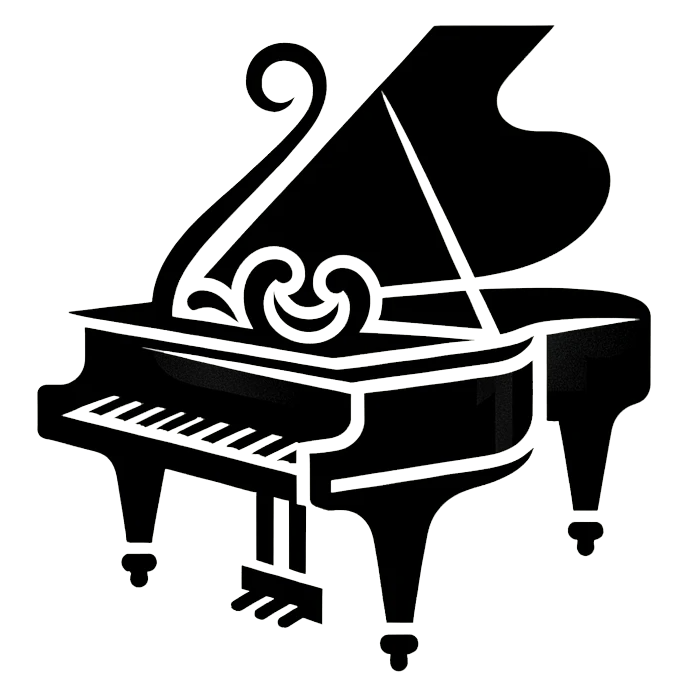🎼 富士市にある「ハウスゾンネンシャイン音楽堂」って知ってる?
実は私も最近まで知らなかったのですが、
富士市厚原にある**「ハウスゾンネンシャイン音楽堂」**という、とっても素敵な音楽ホールに出会いました✨
一歩足を踏み入れると…
演奏者との距離がぐっと近く、天井が高くて開放感たっぷり。
なんだか昔旅したイタリアの教会を思い出すような、温かくて荘厳な空間でした🇮🇹
🎶 音だけじゃない!“空間”が音楽に与える影響って?
音楽を楽しむとき、耳からの情報だけでなく、
**目から入る「空間の印象」**もとても大切なんですって💡
たとえば…
- 視覚から受ける心地よさ
- 音の響きとの一体感
- その場の雰囲気や歴史の重み
こうした要素が合わさって、演奏をより深く感じられるようになるんですね✨
ハウスゾンネンシャイン音楽堂はまさに、そんな“音と空間”の調和がとれた場所でした。

🎹 ホールにある楽器たちも感動モノ!
このホールには、歴史ある貴重な楽器が並んでいます。
- 1910年製のパイプオルガン
- 繊細な装飾が美しいチェンバロ
- 1883年製のブロードウッド社製ピアノ
なんとこのピアノ、あのブラームスが活躍していた時代のものなんです!😳
ブラームスは、「3大B(バッハ・ベートーヴェン・ブラームス)」のひとりで、ロマン派の名作をたくさん生み出した偉大な作曲家🎼
そんな時代の音を、今も生で体感できるなんて…夢のようです💫
🎻 N響メンバーによる感動の室内楽コンサート
この日ホールで行われたのは、
なんと**NHK交響楽団(N響)**のメンバーによる、弦楽三重奏の室内楽コンサート🎻
演奏曲は…
- モーツァルト『ディベルティメント弦楽三重奏』
- シューベルト
- グリエール
繊細で豊かな音が、ホール全体にじんわりと響き渡り、
気がつけば涙がこぼれていました…😭
室内楽は少人数編成だからこそ、ひとつひとつの楽器の音色が際立って、本当に贅沢な音の時間を過ごすことができますね。
🌟 もっと聴きたい、もっと感じたい
次はぜひ、あのパイプオルガンで奏でるバロック音楽を聴いてみたいな…なんて、ワクワクが止まりません🎵
音楽と空間のコラボレーションって、本当に心を動かしますね💗
🎀 おわりに
日常の中にも、こんな素敵な場所や体験がまだまだあるんだなぁと、あらためて感じました。
これからも、心を豊かにする音楽との出会いを大切にしていきたいと思います😊
ぜひみなさんも、ハウスゾンネンシャイン音楽堂で、感動の音楽体験をしてみてくださいね🎶
🎹 富士市のピアノ教室、TAKASEピアノ教室では、
「楽しく音楽を学ぶ」をモットーに、ひとりひとりの個性を大切にした丁寧な指導を心がけています。
初めての習い事にも安心して通っていただける教室です。
📩 お問い合わせはこちらをクリック 👆でメールにて24時間受付中!
ピアノ体験レッスンやご質問など、お気軽にご連絡ください♪